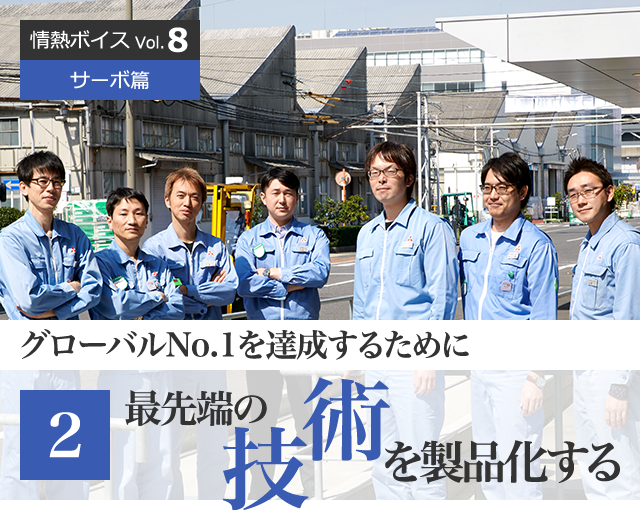情熱ボイス

FA畑のメンバーがほとんどという「新製品企画ワーキンググループ」のなかで、先端技術総合研究所出身の野口琢也は異色の存在だ。FAに限らない全社横断的な基礎研究を行う先端技術総合研究所で、入社から10年以上研究活動に携わっていた野口は、2016年、名古屋製作所ドライブシステム部に異動。と同時に発足したばかりのワーキンググループに参画した。
野口がワーキンググループに加えられたのには理由がある。研究所でバッテリーを必要としないエンコーダの開発を行っていたからだ。モータの回転量や速度を検出するエンコーダは、電源が落ちても位置情報を保持できるように、従来は外付けの電池からエンコーダに電源を供給していたが、電池は定期的に交換しなければならなかった。野口が開発したのは自ら発電する機能を持ったエンコーダで、電池搭載が不要になりメンテナンス工数を削減できる。
「異動は『あっち(名古屋製作所)で製品化して来い』という
意味だと受け取った」
野口は、自分が開発したその技術をサーボモータに搭載すべく、さっそくサーボモータの設計チームとの調整に入ることにした。電池の保守が不要になるのだから、きっと歓迎されるだろう。
しかし、サーボモータの設計チームは
それどころではない難題を抱えていた。
ミクロン単位でサイズの取り合い
サーボモータの開発とりまとめを担当するサーボモータ製造部の土屋文昭は、数年にわたり、複雑なパズルとの苦闘を続けていた。どうすればサーボモータのラインアップを増やすことができるかというパズルである。
ラインアップ拡充は、J5最大のテーマの一つ「グローバルで戦えるサーボ」には必要だ。
以前から指摘されていた課題のため、土屋はワーキンググループ発足前から拡充の方法の検討を進めていたが、お客様へのヒアリングの結果でも、ラインアップへの要望が多く、実現不可避のテーマとなっていた。ただし単純にラインアップを増やすと、個々のモデルのロットは減り、生産工程も複雑化するためコストが上がってしまう。
コストを上げずにラインアップを増やす方法の一つは、部品を共通化することだ。
ラインアップが増えてもそこで使われる部品に共通のものが多ければ、部品ベースではロットはそれほど変わらないことになる。しかし共通化して、一つひとつのモデルに必要な特性を出せるのか。逆に言えば特性を出すためには共通部品の仕様をどう定義すべきか。そのパズルに取り組んでいたのだ。

土屋はカレンダーを見て青ざめた。部品が共通化で大きく変わるならば、サーボモータ本体の設計も変えなくてはならない。J5では大きく分けて6つの機種を展開する予定だが、1つの機種の設計には通常半年から1年はかかる。
しかし2019年春を予定しているJ5の発売までは、
既に2年を切っているのだ。
ワーキンググループ発足前から準備していた部分もあるとはいえ、普通に開発していれば到底間に合わない。
その厳しいスケジュールの中にさらに要件として付け加えられたのが、野口が開発したバッテリーレスエンコーダの搭載だったのだ。もちろん土屋はそれを煩わしいと思ったわけではない。メンテナンス負荷を軽減する野口のエンコーダは、お客様から高い評価を得られるだろう。何としても搭載したいが、現実論として設計作業に全く余裕がないサーボモータにどう搭載するかが、難題となったのである。
土屋を筆頭とするチームと野口を筆頭とするチームは、図面や3Dプリンタで作ったモックアップを前に、ひたすら設計の調整作業を繰り返した。
「エンコーダをこのサイズに収めるためにここの構造を変えられないか?」
「その場合、モータのこの部分をあと1mm小さくしてほしい」
サイズをめぐる両者の攻防はミリ単位、時にはミクロン単位にまで及んだという。

エンジニアリングツールの進化と挑戦
一方、ソフトウェアの方ではグローバル対応への是非が論じられていた。「より多くのお客様へ三菱サーボをお届けしたい」という大方針のもと、モーションユニットのエンジニアリングツールもグローバル対応、具体的には国際規格のIEC61131-3に対応させることは、ワーキンググループの中で確認済みの既定路線だったはず。しかし本当にそれを実行に移すことには、躊躇せざるを得ない事情があった。既存のお客様にも影響があるからだ。

進化と継承の信念を貫く。
エンジニアリングツール「MT Works2」、「GX Works3」の開発を担当するFAソフトウエアエンジニアリング部の服部真充はその二択に悩んだ。IEC61131-3対応を打ち出せば、確かに新規のお客様獲得には効果的だろう。特にグローバルのお客様には有効なはずだ。しかし既存のプログラムを大事に使ってきたお客様には逆効果かもしれない。
そんな中、ワーキンググループで議題として取り上げた。
「両方やる」。それがワーキンググループの結論だった。
背景の一つには、三菱電機のFA事業は「進化と継承」を掲げてきた歴史がある。FA機器の新製品を投入する場合でも、常に旧製品との互換性を確保し、過去の資産を継承しながらお客様が進化の恩恵を受けられる仕組みを約束してきたのだ。
お客様と新しいステージへ
自らも数多くのお客様へ赴き、ニーズを確認した。
その結果、日本のお客様も直接的・間接的の両方で、海外ビジネスの引き合いが増えている事を確認する。お客様の新しい案件受注につなげる為には、 装置自身の差別化だけではなく、商談の入り口も重要であり、そこには現地で使い馴染みのあるエンジニアリング言語への潜在的なニーズがあったのだ。
今お使い頂いているお客様が海外案件を獲得する為には…。
服部が手掛けるエンジニアリングツールの方向性が定まってきた。
但し、従来のプログラム言語の継承性も欠かさず対応し、行き場を失わせない。
そして、我々がお客様を新しいステージへ誘いたい。